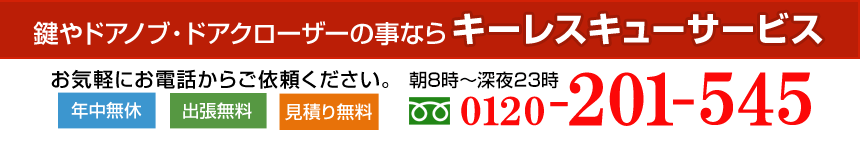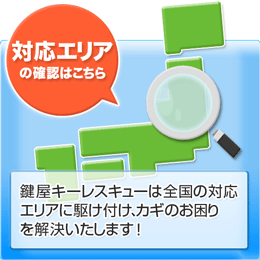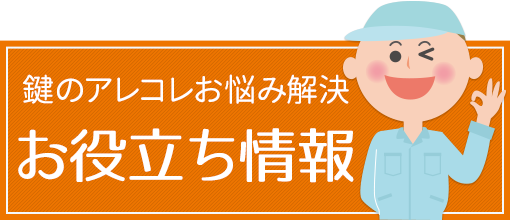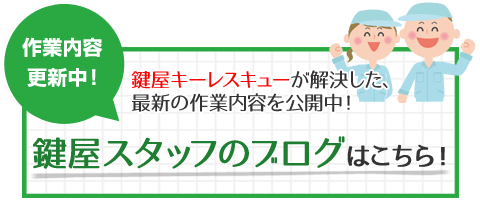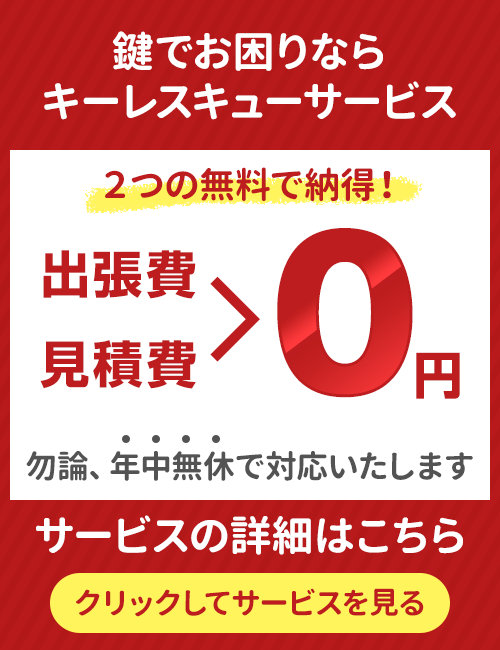クレセント錠(窓の鍵)の鍵交換の方法と注意点について紹介!

クレセント錠は、多くのご家庭(マンションや戸建て)や会社、学校などの窓で使用されており、私たちにとってもっとも馴染みのある鍵です。
しかし、劣化した鍵は防犯性や窓の密閉性を低下させてしまいます。古くなった窓の鍵を交換したい方や鍵付きのクレセント錠に交換したいと考えている方も多いでのはないでしょうか?
クレセント錠の交換は、プラスドライバーが1本あれば自分でも行うことができ、ドリルなどの特殊な工具は基本的には使用しません。
そこで本記事では、クレセント錠の交換方法や注意点などについて詳しく紹介していきます。
目次
クレセント錠とは?
クレセント錠は、他の鍵とは違った独特の形をしており、手で回転させる部分が三日月のようであることから「クレセント」(Crescent =三日月)と名付けられました。クレセント錠はグレモン錠の一種で、ハンドル部分を回すだけで施錠となるタイプの鍵です。
クレセント錠の主な用途は、サッシ窓の防犯対策と機密性の向上で、ほぼ全ての窓に取り付けられているくらい有名な鍵です。
しかし、元々は窓の気密性を高めるため開発された鍵ですので、防犯性はあまり高くはありません。子鍵を用いないため使い勝手は良いのですが、窓ガラスの一箇所を割れば簡単に手が届き、開錠されてしまうので、別途に防犯対策を検討する必要があります。
クレセント錠の交換が必要な理由とは?
一般的に鍵の寿命は10年前後とされていますが、クレセント錠は窓に設置されます。そのため、結露や雨の吹き込みなど、天候の影響を受けやすく、経年劣化の症状が早く現れる可能性も考えられます。
ここからは、クレセント錠の交換が必要になる状況についてご紹介いたします。
クレセント錠の交換が必要になるとき
例えば、下記のような症状が見られるときは、クレセント錠の交換を検討されることをお勧めします。
- サビついている
- カビが多く発生している
- ハンドルに手応えがない(ゆるい)、勝手にハンドルが下がる
- 鍵を閉めても窓の間に隙間ができる。密閉性がない。
クレセント錠の症状によっては、交換ではなく、緩んだネジを締め直すことで改善できる可能性があります。
「ハンドルを動かすと本体部分がガタつく」などの症状があるときは、本体の取り付け部分のネジを締め直してみると問題が改善するかもしれません。
ネジを締めるときは、鍵を開け閉めしながら行い、ゆるんだ本体の位置を調整します。
クレセント錠の半円状の留め具が引っかかる「錠受け」にガタつきがあるときは、錠受けのネジを締め直しましょう。この場合も、鍵を動かしながら錠受けの位置を調整しながら行います。
クレセント錠の故障でよくあるケース
クレセント錠の場合、特に「引きバネ」という部品が折れやすく、新築に住んでから数年でクレセント錠の引きバネが折れてしまったということもあります。
引きバネが折れてしまうと、ハンドルがブラブラした状態になり手応えがなくなります。この場合は、バネだけ交換すれば解決しますが、故障を機に鍵付きやダイヤル付きに交換するのも良いでしょう。
クレセント錠の交換に必要な手順と注意点
ここからは、クレセント錠の交換方法と抑えておくべき注意点を紹介します。
冒頭でも説明しましたが、クレセント錠の交換は自分で行うことも十分可能です。使う道具はプラスドライバーのみですし、部品はホームセンターで購入することができます。
とはいえ、別の種類や新規で鍵を取り付ける際は窓の寸法を測る必要があるので、DIYに慣れていない方や、部品選びに自信がない方は、鍵屋に依頼することをおすすめします。
以下で、クレセント錠の交換に必要な寸法や交換方法について説明しますので、まずは自分で交換できるかを判断してから鍵屋へ依頼するかを検討してみましょう。
クレセント錠交換に必要な寸法とは?
クレセント錠を、鍵付きやダイヤル付きのものなど、新たに取り付ける場合はどの製品を選べば良いのでしょうか。また、もともと付いていたクレセント錠と同じものをつけようとしたとき、廃番になっていることもあります。
クレセント錠を取り付ける際は、窓の寸法を計測する必要があります。新しく鍵を取り付ける際に調べるポイントは以下の通りです。
- ビスピッチ
- クレセント錠の高さ
- 引き寄せ寸法
ビスピッチ

ビスピッチとは、ネジ穴の中心から中心までの長さのことを指します。クレセント錠は、2つのビス(ネジ)で固定されており、窓枠に空いた2つのビス穴の中心までの距離がビスピッチになります。
クレセント錠にビスが見当たらない場合は、カバーが付いていてネジが隠れていることもあるので、カバーを取り外しましょう
クレセント錠の高さ

クレセント錠の高さは窓枠に取り付けたときに、窓枠から鍵のフックまでの距離を指します。台座を下にしておいて、一番高いところまでの長さを測りましょう。この高さがあっていない場合、鍵を回してもフックが錠受け引っかかりません。
引き寄せ寸法

引き寄せ寸法は、クレセント錠を固定しているビスの中心から半円状の留め具のもっとも距離が長い場所までの長さを指します。
鍵を回した時に半円状の留め具がどこまで届くかということですが、長すぎても短すぎてもフックは正常に引っかかりません。
クレセント錠交換の手順
ここからは、具体的にクレセント錠の交換方法について順を追って説明していきます。
- 上側のビスを外す
クレセント錠を窓枠に固定している2つのビスのうち「上のビス」を外します。この際、絶対に2つあるビスの両方を外してはいけません。一つは残し、片方ずつ外していきます。
※古いタイプのクレセント錠は、裏板という部品で窓枠に固定されていることが多いです。上下のビスを両方とも外してしまうと、クレセント錠の裏にある板が窓枠の中に落下してしまい、クレセント錠の取り付けができなくなってしまいます。そのため、必ず片方のビスで裏板を固定しておく必要があるのです。 - 下側のビスを緩める
下のビスを少しだけ緩めます。この際、間違えてビスを外さないように注意してください。緩めたらクレセント錠の上部を手前にずらし、上の部分の窓枠についていたビス穴が見えるようにします。 - 上のビスを緩める
外した上側のビスを窓枠のビス穴にはめて軽く緩めます。 - 下のビスを完全に緩めてクレセント錠を外す
下のビスを完全に緩めるとクレセント錠が外れ、窓枠には上のビスだけが刺さっている状態です。 - 新しいクレセント錠の下のビスを仮止めする
上下を間違えないように注意しましょう。 - 上のビスを外し、新しいクレセント錠の上のビスを仮止めをする
- クレセント錠の鍵をかける
- ビスを本締めする
高さや引き寄せ寸法を調整できるような万能クレセント錠であれば、取り付け後に微調整が可能です。
クレセント錠交換の注意点
クレセント錠を自分で交換するときには、右用と左用を間違えないように注意しなければなりません。クレセント錠には右用・左用があるので、どちらが必要なのかを確認しておきましょう。
クレセント錠の交換費用の相場と節約方法
ここまで、鍵の交換方法について紹介しました。
クレセント錠を交換するにあたり、必要な費用や鍵屋に依頼した場合の相場も気になるのではないでしょうか?ここからは、クレセント錠の鍵交換で必要な費用の目安を紹介します。
クレセント錠交換費用の相場
クレセント錠の交換を鍵屋などの専門業者に依頼する場合は、約¥8,000〜¥15,000となります。しかし、業者によって費用や項目は異なるため、こちらの費用はあくまでも目安ということをご理解ください。
例えば、業者によって「施工料、部品代、主張料」というところもあれば、「調査費、メーカーからの送料、施工費」という内訳の場合もあります。
そのため、業者に依頼する場合は必ず見積もりを取るようにしましょう。鍵屋によっては、出張見積もりを無料で行っているところもあります。
クレセント錠交換費用を節約する方法
ホームセンターなどで鍵を購入して自分で交換する場合、メーカーやクレセント錠の種類にもよりますが、約¥2,500〜¥5,000の費用で行うことができます。
費用面でいえばDIYで済ますのがもっとも節約できますが、鍵屋に依頼したい場合は、複数の鍵屋で相見積もりを取り、費用を比較することでコストを抑えることができるでしょう。鍵屋によっては見積もりを無料で行っているところもあるのでおすすめです。
防犯性の高いクレセント錠の種類と特徴
クレセント錠は古いものは特に防犯性が低いことで知られていますが、最近では防犯性を高めたものが販売されています。ここでは、防犯性を向上させたクレセント錠を紹介します。
ボタン付きクレセント錠
ボタン錠付きクレセントは、ロックボタンが付いているシンプルな構造のクレセント錠で、防犯性能が向上しています。ハンドルを回転させるためにはロックボタンを押す必要がありますが、押さなければハンドルは動きません。たとえガラスを割って手を差し込んでも、ロックボタンを押しながらハンドルを回転させることは難しいため、ガラス破りによる侵入を阻止する可能性が高くなります。
キー付きクレセント錠
キー付きクレセントは、名前の通り鍵穴があるタイプのクレセント錠で、ハンドルを回した後に鍵をかけて固定します。
鍵を開けない限りハンドルを回すことができず、窓を開けられる心配はありません。位置的に窓の外から鍵をピッキングすることも困難で、安全性が高い錠です。
しかし、窓を開け閉めするには子鍵を取り出してくる必要があり、子鍵をなくすと窓を開けられなくなるという管理上の手間があります。
ダイヤル式クレセント錠

ダイヤル錠付きクレセントは、ダイヤルを回して暗証番号通りに合わせないとハンドルを回せず、窓を開けることができないタイプのクレセント錠です。
窓を割って手を入れてもダイヤル部分に手が届かず、番号を合わせることができないため、外から窓を開けることは非常に難しくなります。子鍵を持ち歩く必要がないため、子鍵をなくす心配もなく、管理が簡単な反面、番号を記憶するか、安全な場所に保管する必要があります。
クレセント錠の交換を鍵屋に依頼するメリット
クレセント錠の交換自体はDIYでもできますが、正しく設置できなかった場合、鍵として機能しなくなる可能性もあります。
しかし、専門知識と技術を持ったプロの業者に任せれば安心です。鍵について詳しくなくても、クレセント錠の種類や使用用途に応じて、最適な鍵をお客様に提案することもできますし、設置後のアフターサポートも受けることができます。
特にサッシ自体にゆがみがある時やクレセント錠が錆びついている時は、作業に慣れていない素人が交換するのは困難です。専門的な知識や技術が必要になるため、ぜひ鍵屋にお任せください。
キーレスキューサービスでは、YKKやトステム、不二サッシなど幅広いクレセント錠メーカーからの交換に対応しております。
窓の鍵交換にお困りの際は、お気軽にお電話ください。